デザイン企画
デザインプロデュース
ロゴマーク、ロゴタイプ、ロゴパターンデザイン
アプリケーションデザイン
ウェブデザイン
イラストレーション
写真撮影
ネーミング
キャッチコピー
その他コピー作成
Planning, Produce, Creative Direction: KENICHI OTANI
Graphic design: SEIJI HARIYA
Web design: SEIJI HARIYA & SHINO KIMIYA
Illustration on Web: SORIMACHI AKIRA
Photos on Web: Nacasa & Partners Inc. / Ransack ITO
Corresponding:SHINO KIMIYA
Copywriting:KENICHI OTANI
京都には、当該宿suki1038には、様々な国の方が来訪する。実際に宿泊せずとも、情報として獲得する場合もあるだろう。
自分の体験や得た情報を拡散させるために、世界中の旅する人達が、最も声や表記で再現できるツールは、アラビア数字(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) であると思う。読み方は違うとしても、その数字を自国の言葉の音で誰かに伝えることはできる。書くこともできる。
アラビア数字で流布してもらうとして、ローカルのテロワール的な部分は日本語。日本語、方言を音、表記はローマ字、という組み合わせはこの数年の私のネーミングの考え方だ。
当該ブランドの “1038”。二十四節気をネーミングの一部に入れたいという施主の依頼。二十四節気という概念はこの10年ほど頻繁に目にするようになり、今やそこからブランドが構築できる可能性は薄い。
そこで、二十四節気の24を因数に分解して、3と8にしてみた。
自然現象をサイエンスで解釈していきたい、デザインで処理していきたい、という想いから。ちなみに3月8日は町家の日らしい。
“suki” という言葉は、数寄、から引用した。町家の宿の高級(高額)宿ということで、京都の街には、雨後の筍のように繁茂する町家のリノベーションに対して数寄者の切り口を採り入れたデザインを実現したいと思った。
“スキ” という言葉は、”アソビ”、果ては “スサビ” を語源としている、と言われる。神のふるまい、神に対する祈りや、おもてなしを表す言葉が元となり、やがて、人間自身も遊ぶようになり、”スキ” へと変化してきたという。その後、茶の世界で、亭主の好み(スタイル)、客へのおもてなしのスタイルを数寄と呼ぶようになる。
“スキ” は、自分の中に染み付いた教養や文化、が何気なく相手をもてなしてしまうものではないかと思う。
38に対して1000(千)が足されたのは、もちろん利休の虎の威も借りながら、”千” の持つ、漢字の美しさ、繊細で、無限で、縁起の良い様子を加味したかったからだ。
数寄のコンセプトの一つに、習慣に固執しない、独自の切り口、というのがあるとすると、当該プロジェクトsuki1038のコンセプトの一つには、見慣れたものでも、視点を変えると新しい刺激を私たちに与えてくれるものになる、そんな手法をコンセプトの一つにしている。
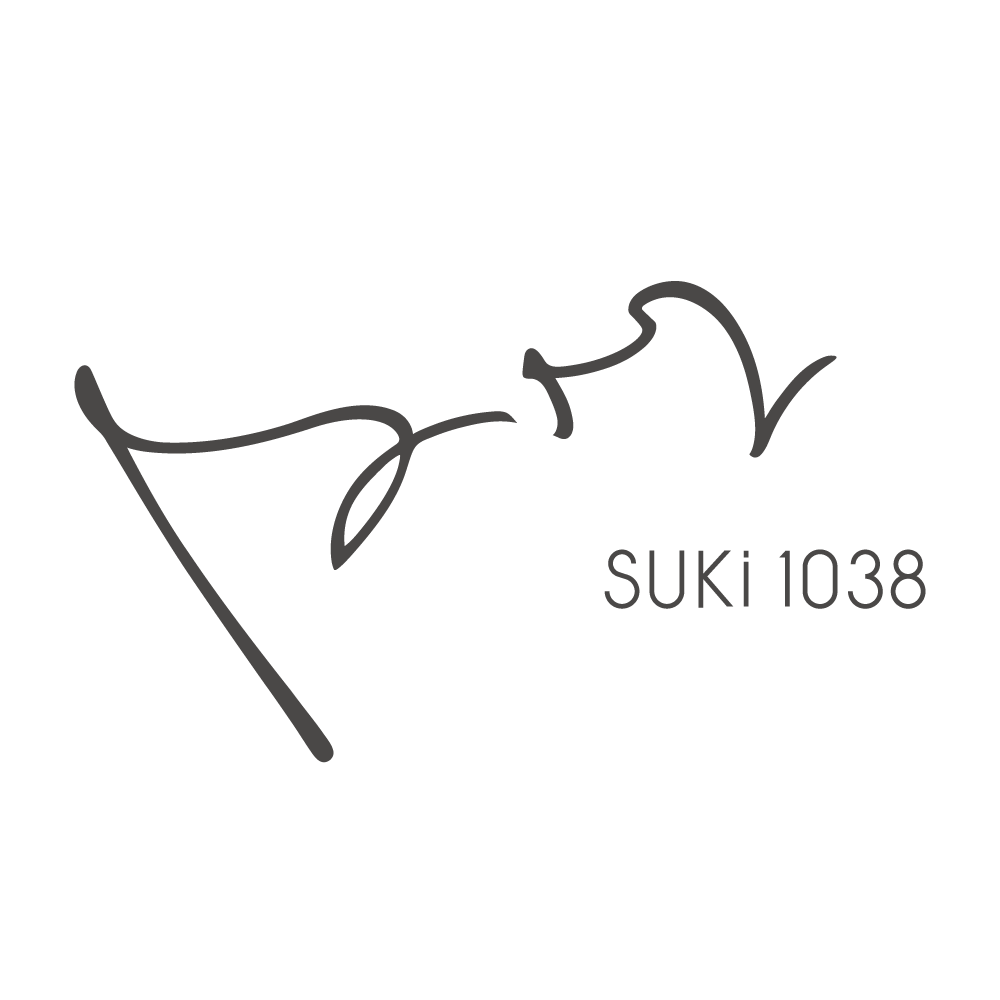

ロゴマークは、私が仕上がりを意識することなく、普段のように書いたひらがなの “すき” を90度回転しただけのものである。
これを最初からひらがなの “すき” であると認識できる人は、未だ私は会ったことがない。大抵の人は、その流れる線からアルファベットの筆記体であろうという先入観で、なんとか、Sと読もうとする傾向にある。
しかし、一度、ひらがなの “すき” を認識すると、思考の轍に従うようにすぐにひらがなの “すき” と読めてしまう。むしろ、ひらがなにしか見えなくなる。
少し右から見ただけで、ひらがなはアルファベットになり、伝統はモダンになる。
もはや見慣れた京都の町家のリノベーションも、新しい視点をもつことで見違えるほどの魅力を発見することができる。
日本の伝統的な吉祥模様の一つ、幾何学模様、”網目” 模様。
一網打尽に絡め取る、無限の連続、から勝利や福を意味する模様として器や衣類に使用されてきたという。
私はこの解釈が、 “縛り” のような窮屈で苦しいもののようにも思え、同じ模様でも ”網の目をくぐる”、”困難をすり抜ける”、という意味と捉えたいと思った。
しかも、その網の目さえも破って、自由な発想や、突破力、といった解放感を持たせた。
“破れ網目文” と読んでいる。
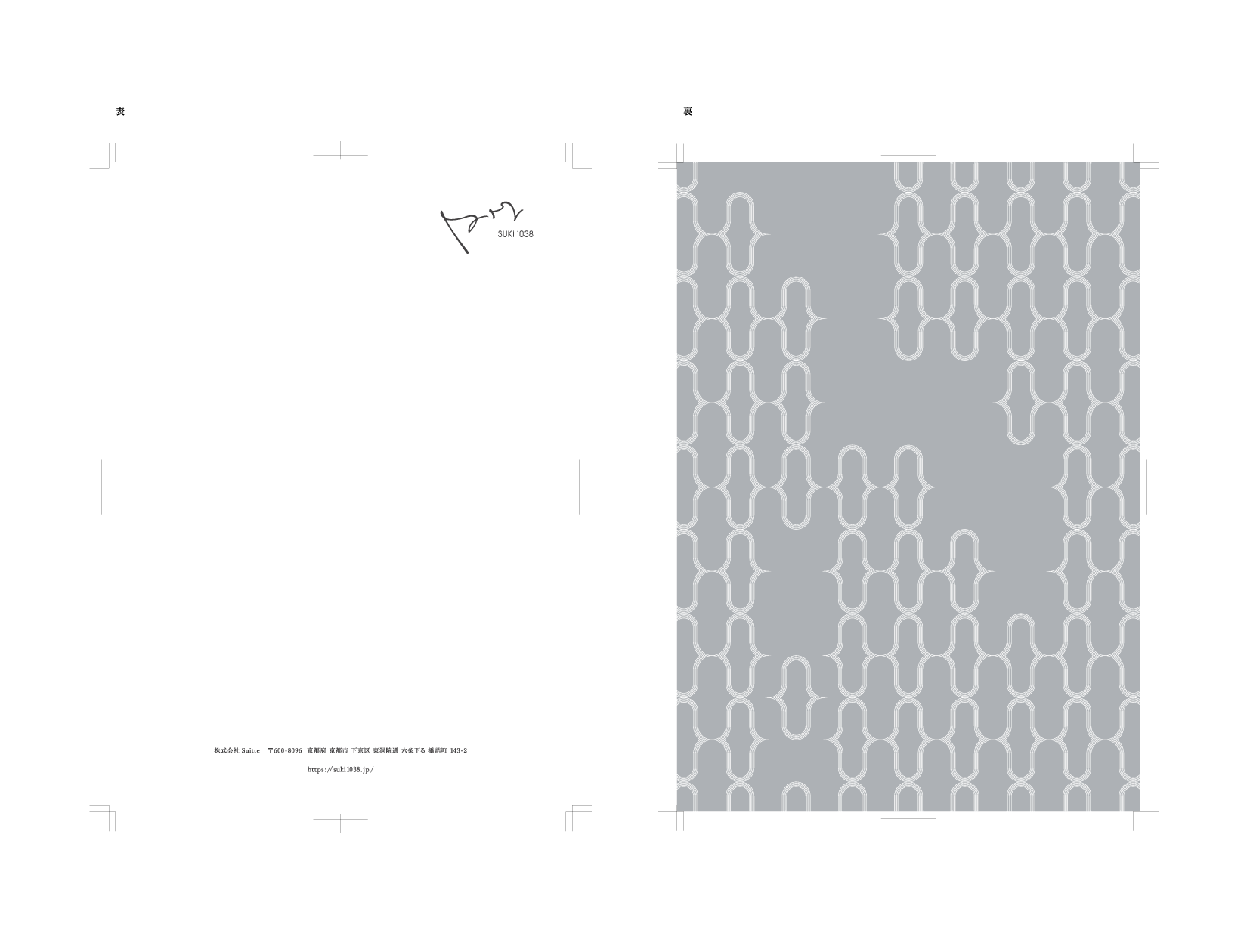
便箋
一方で、網は太古からの人間の道具であり、網目模様は縄文時代の土器にも見られる。そして、北海道や沖縄の伝統模様にも網目模様が独自に変形した模様も見ることができる。
私たちのデザインした “破れ網目文” は、一つのユニット(私たちは、”おばけ” と呼んでいた)を連続して、ところどころに不連続な部分、欠落した部分、隙(すき)をつくって構築されている。そして、”おばけ” の縦使いが通常であるが、それを横使いすること、”おばけ” が連続しない場合の “手” はトゲのように尖らせて、縄文を少しだけ匂わせた。
五重は、枯山水庭園の櫛引きのイメージや、仏教とは言わないが、祈りを重ね、スペイシーな印象を持たせたかった。
Copywriting: KENICHI OTANI
Direction to copywriting in english: KENICHI OTANI
Copywriting in English: Hiroko and Nick
京都弁、京言葉は、いわゆる方言とは少し違う。
イントネーションやアクセント、単語がその地方独特である、といういわゆる方言の持つ特徴に、もう一つ、そして最も重要な要素が加わる。
それは、その言葉の示す内容が、言葉のままストレートに解釈してしまうと、その言葉の発信者の本意とはズレてしまう可能性がある、ということだ。
しばしば例として採り上げられる “ぶぶ漬けでもどうですか”に代表される解釈の方向性のズレだ。言葉の発信者は、「ぶぶ漬けを食べていきませんか?」と誘っているわけではなく、誘い言葉を投げかけて、やんわり断られるのを促し、その場の早期の解散を目論んでいる。それをその言葉の受信者も十分に理解して、そのやりとりの一興に乗る、というものだ。 “ぶぶ漬け〜”のセンテンスそのものの実態は不明であるが、京都にて、このような言葉の本意のやりとりが行われているのは事実だ。
“本意は察してくれ”、 “本意を言葉に露わにするのは雅ではない”、という前提にある言葉の使い方が京言葉のもっとも大きな特徴であろう。
数百年にもわたって同じ土地に同じ人達が過ごしていくための、コミュニケーション手法であり、数百年以上にもわたってこの状態を続けていくのだ、と決めた覚悟のカケラが残っているのだろう。
その京言葉をひらがなで表現し、その本意をわかりやすい英語で表現する、というコンセプトでコピーを作成した。
英語への翻訳は京言葉の解釈を十分に説明、理解してもらった上で、その本意を、世界中でのクリエイティブな仕事経験をもち、今は日本人クリエイターが海外で仕事をしていく際のプレゼンテーションからコミュニケーションの手法までをコンサルティングする日本人の妻と英国人の夫のコンビにお願いした。
なんにもおかまいできしませんけど
Uninterrupted Luxury
当該プロジェクトsuki1038は建物に人が常駐して、あらゆるサービスを施すホテルホスピタリティを行う宿ではなく、建物や部屋を丸ごと宿泊者に委ねて自由にお使いください、という宿である。
だから、 “なにも、おかまいはできませんよ” というコピーなのであるが、これが、京言葉で発言されると、本意は変わってくる。
“なんにもおかまいはできませんけど、室礼(しつらい)として十分に準備してありますので、快適に贅沢な時間を過ごすことができると思いますよ” という本意を含んだ。
声高に “贅沢な時間を過ごせるように準備しています”、と標榜するのは恥ずかしい、控えたい、という生き方なのである。
なんにもせんでよろし
Everything and nothing
これは、京都を、この宿で過ごす京都時間を “リゾート” としている当該宿の活用方法をコピーで表したものだ。
リゾートにおいては、なんにもしない、ことが一番の贅沢な時間。
でも、なんにもしていないようで、一緒に宿泊する相手の顔の表情や、動きの機微をじっくりと傍に感じる時間というのは、充実した時間で、それこそが旅で感じたかったことかもしれない、と思うこともあるだろう。
なんにもしない時間から、本当にしたかったことをする時間が生まれる。
あたらしもんより、ええもんすき
We treasure things made by time
京都人はあたらしもん好きである。
と言うと、京都人の多くは、このように返してくる。
「あたらしもんが好きなん違ごうて、ええもんが好きなんです」
とにかく、はしゃいでいる自分を恥ずかしんでいる人達なのだなあ、と感じる。周囲と自分のバランスを図りながら生きるのである。
数寄、空き、すき
Don’t be afraid of letting go
自分の考えが遊ぶスペースを準備すると、相手のことを想うことができる。
空いた時間を準備すると、本当にすきなことをする時間が生まれる。
そうなったときには、躊躇せずに、そのように行動するのが良い。或いは、行動してしまっている、ぐらいが良い。
知識や経験を教養というシステムとして自身のなかに組み込むことができれば、思考の空きを準備できる。